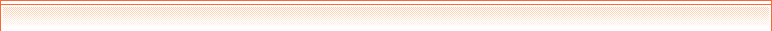2007年6月28日(木)
昨日はじめて『星の王子さま』に感動した。
いままで、何度も手にとって、小学校時代に読んだはずだけど、他の人のように「すごく感動」できずにいて、なんとなく「縁遠い本」になっていたんだけど、昨日本屋に翻訳物が数種類あって、見比べてやっと「読みたかった『星の王子さま』」に出会った。
帰りの電車で一気に読破して、「感動」した。
…思うに、これは「書き手との相性」の問題なんだと思う。
いままで唯一翻訳されていたの『星の王子さま』。
これは、数ある文学のなかから、その原書と「出会う」奇跡を経て、なおかつ「星の」という(原題には存在しない単語ながらわかりやすい)珠玉のタイトルをつけた日本語版「リトル・プリンス」の原点を作った内藤濯氏の功績は偉大だと思う。
もちろん、この「星の王子さま」が好きだという読者もたくさんいる。
そして近年、原作の著作権消滅によって、たくさんの「翻訳版」が出版された。
『星の王子さま』が好きで、その作品によって成長した書き手たちによる「新作」なので、同じ内容がより砕かれた表現で書かれている。
だからこそ、今回「出会う」ことができた。
端的に何がいちばん違うのかというと、「登場人物の心の動きかた」なのだ。
物語の語り手である「ぼく」が、「王子さま」にどう接したか、ことば一つで心の動きがよくわかる「新訳」ゆえに、私もこの「世界」に共感することができたのだと思う。
もちろん、内藤氏の『星の王子さま』は、ロングセラーで、「大切なものは目に見えない」という、不朽のメッセージも伝わってはくるんだけど、いかんせん「大人の視点」が、正直言って苦手なんだなあ(笑)。
もっとも出版された時代の差もあるんだけどね…。
正直言うと「長靴下のピッピ」「シャーロック=ホームズ」でも、全く同じ経験をしている。
いくつかの翻訳を経てはじめて「面白さ」に気がつく、という経験。
どうも私は「語りかけてくれる書き手(翻訳者)」が好きらしい。
そして、「ストーリー」より「登場人物」を描き出してくれる人。
そういう「字組み」だったり、「文字使い」だったり…。(もちろん「挿絵」もあるけど)
そして、そういう「本の顔」を作った編集者の「影のパワー」にもひかれるのかもしれない。
…ということは「編集者との相性」ということなのか??(笑)
「人と本」の出会いのファクターは多種多様。
だからこそ「食わず嫌い」にはなりたくないけど、限られた時間(とお金)のなかから、どうしても優先順位が決まってくる。
私の好きな書き手は「楽天家で負けず嫌い」。そして「子ども好き」。
たぶん…ね♪
PR